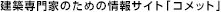- 1.建築家紹介
- 2.豪華な教授陣に恵まれた東大の教育環境
- 3.展覧会巧者
- 4.建築外の分野から来たシェアハウスの概念
- 5.展覧会を実作品のコンセプト・クリエーションに繋げる
- 6.これからの社会における弱者救済の建築にチャレンジ
- 7.建築作品ギャラリー
展覧会を実作品のコンセプト・クリエーションに繋げる
展覧会を実作品のコンセプト・クリエーションに繋げる
「集まって住むを、考え直す」展はキーとなったエキジビション
最初に見た作品は「ROOM 101」で、あのインテリアスケープには驚かされました。次に見たのが展覧会の「ひとへやの森」でした。「ひとへやの森」もシェアード・スペースですか。
猪熊氏:あれはエイブルさんのコンペで、課題が新しいワンルームでした。ワンルームは、ベッドがあって、勉強机があって、テレビがあって、あとはユニットバスだけというものを超えようとすると、定型を崩さないことには新しくなりません。そこでもう少し広がりがある生活を想像した結果、ユニットバスをなくし、水回りも含めてワンルームで成立することを、目指しました。ワンルーム・マンションが嫌いでシェアハウスにガラッと変えたというモチベーションに似ているかもしれません。
シェアード・スペースの方向へ行く過程だったのですね。
猪熊氏:今思えば、そうですね(笑)。その時にはそんなにしっかり考えられていません(笑)。ただ、ああいう空間の感覚が結果的に今も生きています。そういう場でないと、色々な人がひとつの空間の中にゴチャゴチャといながら、ほどほどいい感じに過ごしているという状況はつくりにくいんです。

集まって住むを、考え直す
(C)成瀬・猪熊建築設計事務所

スプリット・ハウス
(C)西川公朗
その次も展覧会で「集まって住むを、考え直す」。これは正にシェアード・スペースの元になっているものですね。この発展型が「LT城西」「スプリット・ハウス」でしょうか。そしてこれらの作品は、木造の柱、梁、ブレースを飛ばしていて、多分おふたりが好きな森のようなインテリアスケープになっています。
猪熊氏:相当直接的に「集まって住むを、考え直す」は「LT城西」「スプリット・ハウス」の元になっています(笑)。
それをスティールでやっているのが「FabCafe Tokyo」「株式会社デンソー名古屋オフィス」「柏の葉オープンイノベーション・ラボ」のような気がします。スティールの作品は天井がかなり機能的で、空中にビームが飛んで天井空間を有効利用している感じです。「SHIBUYA CAST.コレクティブフロア」はひとつの作品の中に色々な特徴が見られます。あれはどういう建物ですか。
猪熊氏:あれは、建物全体としてはわれわれだけでなく、ゼネコンと組織事務所に加えて、ディレクターや8組のデザイナーなど、かなり色々な人が関わっていて、渋谷の再開発で建てたものです。われわれはその住居部分を担当しています。学生よりは年齢の高い人向けの水回り付きシェアハウスです。
成瀬氏:同じフロアに個室が20部屋位あります。だけどここに全員の共用スペースがあって、仕事をしてもいいし、皆でイベントをしてもいいんです。
猪熊氏:ノイズの多い空間をわざとつくろうとしているのは、「ひとへやの森」の時からずっと一緒です。どれだけたくさんの人が、年齢も関係なく、同じ場に入り込めるかということをトライしようとすると、シンプルな空間では自分が美術館の展示品のように目立ってしまいます。どちらかというとノイズがいっぱいあるような空間をつくっておいた方が、どんな人でも入りやすい空間ができ上がります。「ひとへやの森」は、コンセプチュアルに木の枝というわかりやすい一発ネタで、それをつくっています。「SHIBUYA CAST.」では、ダクトや構造体などをうまく利用することもあれば、素材の切り替え方で賑やかさをつくることもあれば、家具の大きさや並び方などにこだわるところもあります。かなり広範囲に、デザインにし得るところを全部使って、ノイジーな空間をつくっている感じです。

FabCafe Tokyo
(C)長谷川健太

株式会社デンソー名古屋オフィス
(C)長谷川健太

柏の葉オープンイノベーション・ラボ
(C)西川公朗

SHIBUYA CAST.コレクティブフロア
(C)渋谷リアルティ(株)

ガーデン・テラス鷹の台
(C)西川公朗
「SHIBUYA CAST.」ではキレイな天井がある部屋と、ダクトが露出している部屋など色々なタイプがありますね。
猪熊氏:天井が一番人の行動とは直接的な関係がありません。最近のようにバリアフリーと言われてしまうと、床に段差は付けにくいし、フレキシブルに色々な使い方をしたいと言われると壁もダメになってしまいます。そうすると天井しか残らないところがあって、そこをどれだけうまく使っていくかというのは大事なテーマだと思います。
なるほど。テラスハウスのシェアを「ガーデン・テラス鷹の台」でやっていて、外部空間をシェアしています。あの空間はいい感じですね。
猪熊氏:それしかやりようがありませんでした(笑)。
成瀬氏:苦肉の策です(笑)。
外部スペースはあったのですね。
猪熊氏:スペースはありました。ただ元は塀が立っていて、道路には出られない形になっていました。その塀を全部切ってしまいましたので、ものすごく空間が変わりました。
公園をつくったようなものですね。
猪熊氏:道を歩いているだけでも敷地内の緑を味わえるので、まず近所の人がすごく喜びました。勝手に敷地に入る人は滅多にいませんけれど、ベンチを置いて座れるようにしています。
テラスハウスの公共スペースなんですよね。
猪熊氏:そうなんです。
次に「天川村南日裏定住促進住宅」。木造であの開口部の大きさはすごいし、ポリカーボネートの納屋も魅力的です。よく考えられていると思いました。
猪熊氏:冬の時期には最高気温が0度という日もあるような寒い地域なんです。もちろん全部高気密高断熱で過ごしてもいいんですけれど、もうちょっと自然を味わいつつ、なるべくエアコンは使わずに、暖かく、気持ちよく住むということが、建築を使ってできたらいいなと思いました。実際に納屋はこれだけ日の光が入るので、温室みたいなものになって、寒くなり始めてもこの中は結構暖かいんです。その暖かい空気を室内にも入れながら、暖房いらずで住む季節を長くしたことが、一番大事なコンセプトです。

天川村南日裏定住促進住宅
(C)西川公朗
エントランスはどこにあるのですか。
猪熊氏:エントランスは納屋の方にあります。
成瀬氏:この地域には波板の小屋が結構あるんです。
猪熊氏:物干しで洗濯物が乾かないくらい寒いところで、似たような設えがいっぱいあります。
この住宅で暮らせるならとUターンする人は結構いるのでしょう。場所はどこですか。
猪熊氏:奈良県です。吉野杉の吉野のさらに奥です。ここではシェア・スペースみたいなものを特徴的につくっていないんですけれど、住み方自体がこの地域らしいことが大事だと思っています。
「LT城西」は正にシェア・スペースでしょう。あの建物のシェア・スペースは垂直方向への吹抜けが大きいですが、暖房などは大丈夫ですか。
猪熊氏:断熱性能をすごく高くしているので、全然大丈夫です。真冬でも昼間は暖房を付けていないですね。日が入るのと、断熱性能がいいのと、熱緩降機を付けているんです。中のエネルギーが換気をしても外に出ないような装置を付けています。

LT城西
(C)西川公朗
写真を見ていると、シェア・スペースだけみたいに感じられて素晴らしい(笑)。
成瀬氏:個室が目立たないようになっています。
個室の広さはどの位ですか。
猪熊氏:7.5畳です。
成瀬氏:共用部分は100m²以上あります。
それは贅沢ですね。この作品はヴェネチア・ビエンナーレで展示したのですね。
成瀬氏:そうです。
そうすると自信作ですね。
成瀬氏:色々なところで展示してもらっています(笑)。

キュープラザ二子玉川
(C)西川公朗
「キュープラザ二子玉川」は商業ビルですが、これは人が入るなと思いました。半外部空間が人を招き込む空間になっています。僕が食事をした地下のアジア系レストランは、二子玉川の有閑マダムでいっぱいでした(笑)。
成瀬氏:同じことを皆おっしゃってくれます。
猪熊氏:実際にすごくたくさんの人が来ているようです。
スティールのフレームと植栽が組み合わされた半外部空間はカッコいいですね。
猪熊氏:フレームと面材をパラパラ散らばらせながら、視覚情報の多い空間を作ることは、一貫して好きですね。

坂の上テラス
(C)西川公朗
「坂の上テラス」はマンションですけれど、2階へ上がる階段部分が半外部空間になって入りやすく、同じ手法でデザインしていると感じました。
- 1.建築家紹介
- 2.豪華な教授陣に恵まれた東大の教育環境
- 3.展覧会巧者
- 4.建築外の分野から来たシェアハウスの概念
- 5.展覧会を実作品のコンセプト・クリエーションに繋げる
- 6.これからの社会における弱者救済の建築にチャレンジ
- 7.建築作品ギャラリー
TOTOホームページの無断転用・転記はご遠慮いただいております。