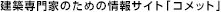- 1.建築家紹介
- 2.豪華な教授陣に恵まれた東大の教育環境
- 3.展覧会巧者
- 4.建築外の分野から来たシェアハウスの概念
- 5.展覧会を実作品のコンセプト・クリエーションに繋げる
- 6.これからの社会における弱者救済の建築にチャレンジ
- 7.建築作品ギャラリー
建築外の分野から来たシェアハウスの概念
建築外の分野から来たシェアハウスの概念
「シェアする場をつくること」が設計のモットー
現在、スタッフは何人ですか。
猪熊氏:自分たちを入れて11人ですね。
アトリエ派の事務所では10人越したら大きい方です。なかなかスタッフの人数が10人を越す事務所はありません。前回インタビューした納谷建築設計事務所は作品がもうじき200件になりますが、スタッフの人数は9人です。
成瀬氏:ええ!どうやって仕事を回しているんでしょう。
事務所はずっとこの場所ですか。
成瀬氏:さまざまな場所を転々としています(笑)。
猪熊氏:小さな事務所からスタートしているので。
成瀬氏:最初は私の家でやっていました。阿佐ヶ谷でした。

事務所の外観

事務所風景
事務所をつくってから数年は、仕事がなかったということでしたが…。
猪熊氏:全然ありませんでした(笑)。
皆さんそうなんですね。最初は親戚の家を設計するというのが多いですね。
成瀬氏:それに気付きましたが、私たちにはそういう人がいないんです。庶民だとそういうところがね(笑)。そういうことはなかったですね。
そうすると今までの仕事は、例えばコンペで取るとか、コネクションで取るとかありますが、どういうケースが多いですか。
成瀬氏:色々ありますね。
猪熊氏:公共のプロポーザルは倍率が高いですが、民間の指名コンペをいただくことが結構あって、そうすると3、4社なので、まあまあな確率で取れるようになりました。
指名コンペに入るというのはすごいですね。さらに公共のコンペで指名に入るとすごいんですけれどね。
猪熊氏:そこまでにはまだいかないですね(笑)。
もう時間の問題で、そのうち指名されますよ。現在の作品数はどの位ですか。
猪熊氏:決して多くはありません。例えば新築なんてビックリするほど少ないですよ(笑)。住宅3つと「りくカフェ本設」「LT城西」「天川村南日裏定住促進住宅」「坂の上テラス」「キュープラザ二子玉川」の8個しかありません。

りくカフェ本設
(C)西川公朗
その分リノベーションが多いのでしょう。今はリノベーションの時代だと言われています。時代の先端を疾走しているレム・コールハースが「新しいデザインを考えることに疲れた」と言っています。
成瀬氏:レムでも疲れるんですね。
リノベーションがいいと彼は言っています。彼がデザインしたミラノの「プラダ財団キャンパス」は、古い建物を壊さず要所要所に新しい建物を巧みに入れ込んで、新旧のマッチングが抜群でした。
猪熊氏:彼のリノベーションはカッコいいですよね。特別です。
成瀬氏:リノベーションや内装は多いですね。内装というのはリノベーションになるのかしら。
猪熊氏:構造に触れていない内装もそうですね。店舗やオフィスの内装も結構あるんです。

プラダ財団キャンパス
でも実は構造に触れているものにすごい作品がありますね。構造は得意なんですよね。
猪熊氏:その辺は楽しんでやっています(笑)。
「シェアする場をつくること」を設計のコンセプトにあげていますが、どういうところからそれを発想したのですか。
成瀬氏:仕事がなかった頃に、あるワンルーム・マンションの依頼を受けたんです。真面目に設計しているのに、なかなか事業収支が合わなくて、結局事業がストップすることになったんです。その時にたまたまそれとは別に若いシェアハウスを運営している人から、「これからシェアハウスをやっていきたいんだけれど、リノベーションするに当たって、何か建築的なアドバイスをもらえないか」と事務所に相談が来たんです。その頃、シェアハウスという言葉を巷では聞いていましたけれど、建築業界ではまったく取りざたされていませんでした。新しい暮らし方というのが、建築業界とは別のところで実践されているというのを見て、すごく進んでいると感じました(笑)。そこから興味をもったというのが大きいと思います。
素直ですね(笑)。建築的にこれからの対象となるという判断で、柔軟に取り組んだわけでしょう。
成瀬氏:それで止まりかけていた集合住宅のプロジェクトに、シェアハウスの案を勝手に設計して、持って行きました(笑)。そうしたら、本当に事業収支が合って、実際に動きそうになったんですけれど、土地の売買の関係で動かなくなって、結局は止まってしまいました。その時に新しい暮らし方が実現できていることに加えて、経済的な合理性もあったというのが、すごく面白くて、これを考えてみたらいいかもしれないというところから始まりました。
こちらの事務所では、「シェアする場をつくること」をコンセプトにあげています。また建築家の個性は形や素材に現れるけれど、私たちが突き詰めるのは「そこにどんな営みを作りだすか」であるということが語られています。さらに業務として"つくるをサポート(デザイン・設計・監理業務)"、"企画をサポート(プロデュース業務)"、"学ぶをサポート(セミナー・レクチュア・ワークショップ業務)"があげられています。これらは別の仕事として考えているのですか。
猪熊氏:連続はしているんですけれども、設計に入る前の段階が多いかもしれません。プロデュースというのは、事業とその事業にかかるお金と事業で結果上がる利益とを含めて、こういう設計があなたの買おうとしている土地だとできますよとか、もうちょっと個性的な場づくりをする場合にはこういう施設を入れた方がいいですよとか、そういうことをこちらからアドバイスするという、設計が始まる前の前提条件をつくることそのものも、仕事にしていて、かなりそういう部分が増えてきています。これは成瀬がしたシェアハウスの話と一緒で、よくある条件設定になってしまうと、いくら頑張っても、その枠の中でちょっと違うものにしかなりません。大学の課題で言うと、課題そのものをつくるくらいの意気込みで上流から関わらないと、今までなかったような場づくりに繋がらないとよくわかったので、プロデュース的な立ち位置の仕事を積極的にやっているというのがあります。


イトーキでのワークショップ風景
他の建築家も建築と一緒にプロデュース的な仕事をする機会があると思いますが、こちらの事務所ではセミナーやレクチュアもしているのでしょう。
猪熊氏:企業の研修のお手伝いは結構やりますね。
ハードの仕事だけでなくソフトの仕事がまだあると。
猪熊氏:そうですね。もっと広げて行きたいという野心はあります。なかなか限界があってゆっくりですけれど。
シェアというのはコミュニティとか、共同体という考えとは違うのですか。
猪熊氏:もうちょっと緩い概念かもしれないと思っています。コミュニティみたいなウエットなものも含んでいるとは思うんですけれど、もうちょっと一時的なものだったりします。最近、シェアリング・ビジネスで、AirbnbとかUberとかの話が出ますけれど、一時的に乗り合わせたりするだけのものも、シェアのひとつになっているのでもわかる通り、そんなに定義がなく、作りながら定義して行けるところが魅力です。
ホームページで作品を見ていくと、シェアード・スペース、プライベート・ハウス、プロダクトなどのカテゴリーがあるなかで、ほとんどの作品がシェアード・スペースに入っています。でもこちらの事務所のシェアード・スペースにはもう少し特殊性があるのではないですか。
猪熊氏:なるほど。ホームページのつくり方は半分戦略的にやっているというか、これまであったパブリック・スペースもシェアード・スペースとして扱っています。実際にはパブリックとプライベートの間くらいの新しい繋がりをどうつくるかという部分が興味のメインではあります。オフィスくらいのある限られたメンバーに対して、もうちょっとコミュニケーションが活発化できるような場所をつくったりとか、本来パブリックを担わなくてもいいような一民間企業がもう少し地域づくりをやるようになったりとか、色々な枠組みの中で、本当の意味での公共がやるパブリックと、家族が家を建てている単なるプライベートとの、間のバリエーションをたくさんつくることを目標にしています。ただ本当のパブリックを公共から頼まれることを目標にしないのかというと、むしろ最終のゴールはちゃんとそういうもので、われわれらしい力作をつくるということは目標にしたいと思っています。そういったことに繋げるために、ホームページにはシェアード・スペースが多くなっています。
ストラテジックなホームページつくりですね。
猪熊氏:最後はそこに市庁舎や美術館も入ってきたら面白いと思っています。
- 1.建築家紹介
- 2.豪華な教授陣に恵まれた東大の教育環境
- 3.展覧会巧者
- 4.建築外の分野から来たシェアハウスの概念
- 5.展覧会を実作品のコンセプト・クリエーションに繋げる
- 6.これからの社会における弱者救済の建築にチャレンジ
- 7.建築作品ギャラリー
TOTOホームページの無断転用・転記はご遠慮いただいております。